Sony RX1R III

いつかは……と憧れていたカメラを、ついに買ってしまいました。
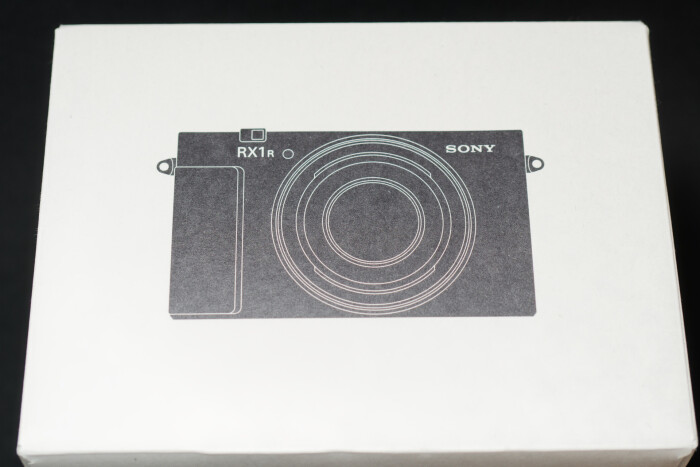
61MPのフルサイズセンサーとZEISS Sonnar 35mm F2の単焦点レンズを手の平サイズに凝縮した、ソニーの新型コンデジです。
RXシリーズは私の好みにドンピシャで、コンパクトなRX100シリーズは初代と三代目、高倍率なRX10は三代目を購入して愛用しています。フルサイズで単焦点なRX1は、いつかは、と憧れてはいたものの、新製品の音沙汰がなくなってから長い年月が経過し、後継機は出ないのかと半ば諦めていたところです。リリースを見たときは嬉しかったですね。「これは買うしかない」と決心しての購入です。RX1R IIIを買ってしまえば、X100などのXシリーズが気になることもなくなりますし、無駄遣いが減って健全。マウントを増やすと維持が大変ですからね。
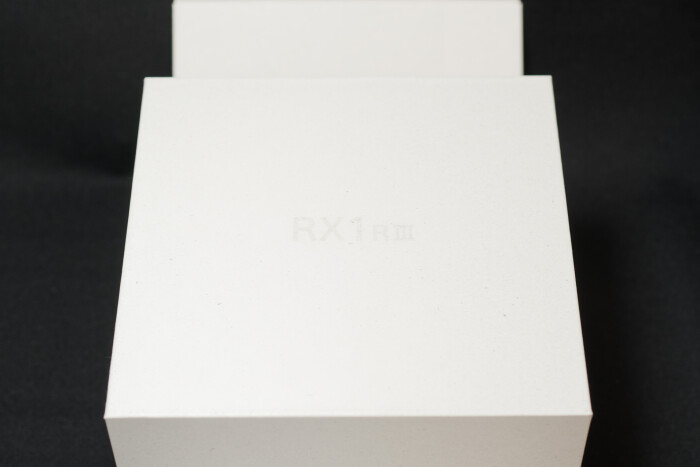
梱包は白を基調にしたシンプルなデザインです。環境配慮ってやつですね。

箱の中からは、まずカメラ本体が登場です。

カメラ本体の下には、アイピースカップ、バッテリー、ストラップなどの付属品が入っていました。

基本的なスタイルはRX1シリーズを引き継いでいます。上面がフラットになった点が大きな違いです。サイズ感は、α7C IIを一回り小さくしたといったところ。重さは、バッテリーとメモリーカードを入れて500g程度と、レンズなしのα7C IIと同じくらいです。見た目がコンパクトだからか中身の詰まったズッシリ感がありますが、スペックとしては軽量です。

グリップ部分はドットパターンが刻まれています。薄いですが滑りにくく、意外としっかりグリップできます。ストラップ取り付け用の三角環は、動きにくく音が出ないタイプです。バッテリーはNEXから使われてきたNP-FW50です。先代で使われていたNP-BX1ではBIONZ XやAIプロセッシングユニットの消費電力を賄い切れなかったのでしょう。

上面フラットなデザインはスッキリしていて素晴らしい。新開発のアイアンブラック塗装は、見た目の質感だけでなく手触りもよくて快適です。EVFはポップアップ式から固定式に変わりました。固定式の液晶ディスプレイとあわせて、小型化に貢献しているそうです。レンズ交換のないレンズ一体型カメラということで、レンズとセンサーの位置調整は一台ずつ手作業で調整しているとのこと。本体前面端よりも内部までレンズが詰まった構成だそうです。

操作部はオーソドックスな作りです。モードダイヤル、露出補正ダイヤル、レリーズ対応のシャッタボタンに電源スイッチです。カスタムボタンはC1の他に2つ、合計3つ用意されています。C1のデフォルト設定はクロップ切り替えになっています。ボタン操作ひとつで50mmと70mmにクロップできるので、単焦点レンズながらも画角を変えて撮影が楽しめます。

背面も見慣れたαシリーズの操作系です。C2ボタンは動画用のデザインが最近の流行ですが、RX1R IIIはスチルメインということでカスタムボタンのデザインになっている点がこだわりポイント。液晶ディスプレイはチルトできた方が嬉しいですが、この仕上がりを見ると小型化のための割り切りとして納得です。
液晶保護は純正の保護ガラス「PCK-LG1」を貼っておきました。

レンズ鏡胴の操作系は、操作リングの他にマクロ切り替えリングと絞りリングが備わっています。マクロモードへの切り替えは手動ですが、約14cmまで寄れるのは心強い。テーブルフォトで活躍しそうです。

レンズは引き続きのZEISS Sonnar 35mm F2です。61MPのセンサーに見合った実力があると判断されての続投なのでしょう。絞り羽根は9枚で、G Masterに比べると控えめ。実際の撮影で試してみるのが楽しみです。

α7CRにZEISS 35mm F2.8を組み合わせた状態と大きさを比べてみました。RX1R IIIの小ささが実感できます。特にボディ部分の薄さが際立っています。α7CRにはボディ内手ぶれ補正、バリアングルの液晶ディスプレイ、握りやすいグリップと大型のバッテリーが備わっているので単純には比較できませんが、一段明るいレンズを搭載してこのサイズ・重量という点には驚きしかありません。
憧れだったカメラをついに手に入れました。常に持ち歩けるフルサイズセンサーのカメラとして、撮影が主目的ではないお出かけに連れ出して撮影を楽しみたいと思います。














